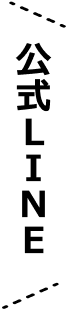![]() 記事
コンプライアンスシリーズ 第二章【ご利用者との関係性について】
記事
コンプライアンスシリーズ 第二章【ご利用者との関係性について】
コンプライアンスシリーズ 第二章【ご利用者との関係性について】

今回からは、ご利用者との関係性についてコンプライアンスの観点から全4回に分けてお伝えしていきます。
① 契約時の重要事項説明の適正な運用方法について
デイサービスにおける利用者との関係性を築くうえで、最初の接点となるのが「契約時の重要事項説明」です。
利用者本人や家族に対し、サービス内容や費用、利用条件などを正しく説明することは、法的な義務であると同時に、信頼関係の基盤をつくる大切なプロセスです。
適正に運用できなければ、後々のトラブルや不信感を招く要因となります。
そのため、説明内容や方法、記録の残し方まで含めて、組織的に徹底することが求められます。
まず大前提として、重要事項説明は「形式的に説明を終えること」が目的ではなく、「利用者が理解・納得して契約すること」をゴールに据える必要があります。
利用者は高齢者が中心であり、聴覚や視覚、認知機能に制限を持つ方も少なくありません。
したがって、専門用語を多用するのではなく、誰にでもわかる言葉に置き換えて伝えることが重要です。
例えば「加算」や「介護報酬」といった業界用語は、「国のルールに基づいて決められた料金です」など、平易な言い回しに置き換える工夫も必要です。
次に、利用者が「理解できているかどうか」を確認する姿勢が欠かせません。
単に説明して同意書に署名してもらうのではなく、「ご不明な点はありませんか」と確認を挟むことで、理解度を確かめられます。
利用者本人が答えにくい場合には、家族にも確認を取りながら進めることが適正運用につながります。
記録の面では、担当者会議で説明を行った場合など、誰がいつ、どのように説明を行い、利用者や家族からどのような質問があり、どのように回答したかを「担当者会議の記録」などとして残すことが大切です。
これは、後に「聞いていない」「説明を受けていない」といったトラブルが発生した際に、事業所を守る根拠にもなります。
さらに、契約時だけでなく、サービス内容や料金に変更が生じた場合には、速やかに再説明を行う体制を整えることも求められます。
例えば、加算の新設や廃止があった場合、介護報酬改定に伴う料金変更がある場合など、利用者に不利益が生じないよう、正確かつ早期に情報を共有しなければなりません。
適正な重要事項説明の運用は、単なる手続きではなく、利用者と事業所が「対等な立場で契約関係を結ぶための基本姿勢」です。
ここでのやりとりが、信頼関係を築けるかどうかが、その後のサービス利用全体の満足度や安心感に直結します。
事業所はこの点を強く認識し、職員教育やマニュアル整備を通じて、全職員が一貫した対応を行えるよう体制を構築していく必要があります。
# Other article
関連記事